焙煎豆の香りがふわりと肩に落ちてきて、まるで“今日という一日の軸”をそっと整えてくれる儀式のようでした。
年間200店舗以上を巡る取材の中で、僕はいつもまずこの香りに耳を澄ませます。ブランドの思想は、匂いと空気に必ず滲むからです。
カップを受け取ると、ラテの温度が手のひらから胸の奥へとやさしく沈んでいきます。
その瞬間、ふと小さな疑問が立ち上がる。
「この一杯の“原価”って、いったいどこまでがコーヒーで、どこからがスタバという文化なんだろう?」
広告代理店時代、数多くの飲食ブランドの原価・価格設計に携わり、チェーンストアの裏側を見てきました。
だからこそ思うのです。
スターバックスの価値は、豆の価格表では語りきれない——それどころか、数字の外側にこそ真実がある。
この記事では、チェーン文化研究家としての知見と、現場取材で得た一次情報をもとに、
「スタバの原価は高いのか、安いのか」という素朴な問いから出発し、
その“値段の裏側”にあるブランド哲学と、おいしさの正体を静かにひもといていきます。
スターバックスの原価は本当に高いのか?数字から見る“意外な事実”

朝のスターバックスで、湯気の向こうにある“静かな時間”を味わっていると、
ふと胸の奥でスイッチが入るように、ある疑問がむくむくと顔を出すんです。
「この一杯、原価はいくらなんだろう?」
僕はこの問いが大好きです。ちょっと禁断めいていて、でも知れば知るほど世界が広がる。
しかも、スタバの場合は“予想をいい意味で裏切ってくる”からワクワクするんですよね。
一杯あたりの原価は“想像以上に安い”
スターバックスの財務データを追っていくと、まず驚くのが原価の構造です。
アメリカで公開されている「COGS(売上原価)」は、全世界の豆・ミルク・フードの総コスト。
それを“ラテ1杯あたり”に換算していくと、経済メディアの分析では
「一杯のコーヒー豆原価は数十セント(数十円)」
という数字が何度も出てきます。
初めてこのデータを調べたとき、僕は思わず「え、そんなに低いのか」と声が漏れました。
でも同時に、「ここからが面白いんだよな」とニヤけてしまった。
なぜなら、ここから“値段の裏側の物語”が一気に動き始めるからです。
原価率は公表されない。“豆だけでは価格が決まらない”から
ここでもう一つ、ワクワクする事実があります。
スターバックスは一杯の原価率を公表していません。
「ラテの原価率は?」「フラペチーノの原材料コストは?」
——その答えは公式には明かされない。
でも、それには明確な理由があります。
スタバの価格は“豆の値段だけ”では決まらないんです。
実際に裏側を探っていくと、値段にはこんな“見えない原価”がぎっしり詰まっています。
- バリスタの教育・トレーニング
- 店舗のデザイン・設備投資
- 一等地に出店するための高い賃料
- ブランドを維持するためのマーケティング費用
- グローバルレベルの品質管理体制
- アプリ・モバイルオーダーなどのITインフラ
こうした“目に見えないコスト”をたどっていくと、
「原価率という一つの数字では語れないブランドなんだ」と、むしろ胸が高鳴ってくるんですよね。
他の飲食チェーンと比べてどうなのか
ハンバーガーチェーンやファミレスは、食材・人件費・その他コストの構造が比較的明確です。
だから原価率である程度語れる。
一方のスタバは、“空間価値”と“体験価値”のウェイトが圧倒的に大きい。
つまり、数字だけを追っても本質に辿りつけない。
その“探究の余白”が、僕にとってスタバというブランドを追い続けたくなる理由でもあります。
そしてカップを手にしたとき、じんわりと伝わる温度に、ハッとするんです。
「ああ、これこそが原価には載らない価値なんだ」と。
その一瞬を味わうたびに、原価では測れない満足という言葉の意味が腑に落ちていく気がします。
原価率だけでは語れない。スタバの“価格の正体”はどこにあるのか
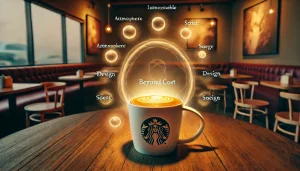
ラテの香りが立ちのぼる瞬間、いつも僕は胸がざわつきます。
「さあ、ここからスタバの“面白い部分”に入っていくぞ」という、あの独特のワクワク感です。
というのも、スターバックスの価格って、ただの数字じゃないんです。
まず手放したいのは、飲食業界でよく言われる
“原価=価値”という単純な図式。
これを持ったままでは、スタバの世界は一生見えてきません。
なぜなら、スタバの価格は「豆の値段」だけでは1ミリも語れないからです。
スタバは“コスト+利益”で価格を決めていない
僕が広告代理店で飲食チェーンの価格設計に携わっていた頃、
ほとんどの店舗は「食材原価 × ○倍」という考え方で値段を決めていました。
いわゆる「コスト+マージン」方式ですね。
でもスターバックスは、そこから完全に外れた場所にいます。
彼らの基準は、
「この一杯でお客がどんな価値を受け取れるか」。
ここがもう圧倒的におもしろい。数字の向こうに、ちゃんと「人」がいる価格なんです。
専門的にはプレミアム価格戦略と呼ばれますが、
スタバは創業期からずっとこの路線をブレずに貫いている。
だから、
原価が安い=値段も安い
という方程式が通用しない世界にいるわけです。
プレミアム価格戦略とは?
プレミアム価格戦略を噛み砕いて説明すると、こんな感じです。
– ブランドを信頼している人が多いほど
– 値段に対する“敏感さ”が低くなり
– 高くても「まあ、スタバだしね」と受け入れられる
スタバのラテが他店より50〜150円高くても売れ続けるのは、まさにこの構造。
そして僕は、このロジックがわかった瞬間にスタバの価格が一気に“生き物”みたいに見えてきて、興奮しました。
味の良さだけの話じゃない。
「安心」「一貫性」「日常の中の小さな儀式」——。
こうした心理的価値が積み上がることで、価格が自然に成立しているんです。
空間・体験・ブランド価値が価格を形づくる
スタバの本当の価格要素は、実はドリンクの外側にあります。
僕が取材で何十回も痛感してきた部分です。
- 照明の色や落ち着く明るさ
- ソファや椅子の“沈み込み具合”
- 作業のリズムを邪魔しないBGM
- 気持ちを整えてくれるバリスタの接客
- 季節ごとに用意されるストーリー性ある商品
- 店に入った瞬間にふわっとくる“あの匂い”
これらすべてが、「飲み物」ではなく「体験の価値」をつくっています。
スターバックスは「第三の場所」という文化そのものを売るブランド。
この視点を知った瞬間、価格の意味がまるごと変わるんです。
立地・人件費・教育コストという“見えない原価”
そして、スタバの“裏側”をたどるとさらに面白い。
僕が企業取材で何度も聞いた事実ですが、スタバは「目に見えない投資」がとんでもなく大きい。
- 都市一等地に店を構えるための賃料
- 数ヶ月単位で行われるバリスタ研修
- 全国で統一された店舗デザインの開発
- グローバル品質を保つ管理体制
- サステナビリティへの投資
- アプリ・モバイルオーダーのIT基盤
これらは原材料原価には入らないけれど、
「安心」「おいしさ」「一貫した体験」のための土台になっています。
だからスタバは、原価率だけで語れない。
むしろ、価格の裏側を知れば知るほど「うわ、スタバって面白いな」と興奮してくるんです。
カップを手にすると伝わってくるあの重みまで、ちゃんと“理由”がある。
それを知ってから飲むと、その一杯の物語がはっきり見えてくるようになります。
“原価は安いのに高く感じない”理由──スタバが選ばれ続ける心理構造
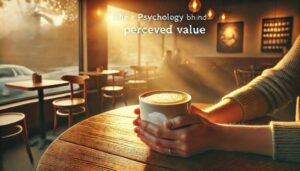
ラテのカップを掌にのせた瞬間、僕はいつも「よし、ここから面白いところに入っていくぞ」という気持ちになるんです。
ほんのり丸いフォルムと温かさだけで、人ってこんなに気持ちが整うんだ、という“スタバの魔法”がある。
しかも僕らは、その一杯に600円前後を迷いなく支払っている。
これって冷静に考えるとかなり不思議な現象です。だけど、どこか自然でもある。
なぜそんなことが起こるのか。
この問いを深掘りしていく瞬間が、僕は本当に好きです。だって、ここから“スタバの心理構造”が一気に見えてくるから。
その答えは、まさに僕たちの心理の中に隠れています。
日常を整える“儀式性”があるから
まずひとつ。スタバに寄るという行為は、多くの人にとって単なる「コーヒーを買う」という作業じゃない。
むしろ、「日常をスタートさせる儀式」に近いものなんです。
- 出勤前に気持ちをリセットするスイッチ
- 仕事と仕事の間を区切るためのアイコン
- 週末に“ちょっといい自分”になるためのごほうび
- 自分を取り戻すための“静かな間(ま)”
この“儀式性”が生まれるブランドって、本当に一握りだけ。
原価とは一切関係ない領域なのに、体感としてはむしろ一番価値がある部分なんですよ。
同じカフェラテでも、コンビニで買うものとは心の役割がまったく違う。
この違いを理解した瞬間、スタバの価格の見え方がガラリと変わります。
“自分へのごほうび”としての価格弾力性
それに、スタバの価格は僕らの行動心理ともガッチリ噛み合っています。
特に、マーケティング心理学でいう「ごほうび需要」と驚くほど相性がいい。
人は——
- ちょっと疲れたとき
- 気持ちを入れ替えたいとき
- 自分を励ましたいとき
無意識に、いつもより少し高いものを選ぶ傾向があります。
「よし、これで頑張れる」というあの小さな感覚のために。
スタバのカップを手に持ったときの“わずかな高揚感”は、まさにその心理をくすぐってきます。
原価では測れない価値の代表例ですね。
安心のブランド体験が“納得感”を生む
さらに言うと、スターバックスは“安心”を徹底的に設計しているブランドです。
ここは取材するたびに感心する部分。
- どの店舗に行っても味が安定している
- 接客の質が一定以上で“外れ”がほぼない
- 知らない街のスタバでも「ここなら大丈夫」と思える
これらはすべてブランド体験の一貫性と呼ばれるもの。
この安定感があるから、「ちょっと高いけど納得できる」という心理が生まれるんです。
この“安心コスト”こそ、原価には表れないけれど価格を成立させる超重要な要素。
僕はこれを知った瞬間、「あ、スタバの価格はすごく合理的なんだ」と膝を打った覚えがあります。
「原価が低くても、あなたの時間は高く評価されている。」
これがこの記事全体を通してのメッセージです。
スタバの価格は、飲み物そのものへの対価ではありません。
スタバが値段をつけているのは、
「あなたの時間」なんです。
だから原価が安くても、価格が高くても矛盾しない。
むしろ、価値がちゃんと噛み合っているからこそ、スタバは何年も、何十年も選ばれ続けている。
この構造を知ると、スタバの一杯を手にした瞬間の“ちょっとした特別感”が、
ただの気分ではなく理由のある満足だったんだと実感できます。
ラテ一杯の中にある“ブランド哲学”──原価では測れない価値を言語化する
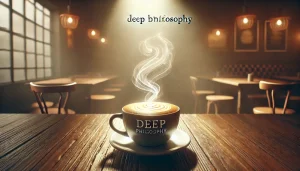
スターバックスのラテを手にすると、僕はいつも心のどこかがうずきます。
「さあ、ここからスタバの“核心部分”に触れられるぞ」という、あの独特のワクワク感です。
ただの飲み物に見えて、実はとんでもない思想が仕込まれている——これを知ってしまうと、もう普通のコーヒーには戻れません。
原価を調べることはできても、スタバの哲学だけは数字では分からない。
これは、実際に空間に身を置き、サービスに触れ、カップを口に近づけて初めて見えてくる“体験の領域”なんです。
香り・温度・接客…五感すべてで価値をつくるブランド
スターバックスを語るうえで、僕がいつも強調したくなるのがここ。
スタバはコーヒーを売っているように見えて、実際には「五感のデザイン」を売っているブランドです。
- ラテの香りがスッと立ち上がる“あの瞬間”
- 手のひらにぴたりと収まるカップの温度
- バリスタの声のトーンや、ほんの数秒の間(ま)
- 店のリズムを決めているBGMのテンポ
- 気持ちを落ち着かせるゆったりした空気の流れ
こういう要素が少しずつ、でも確実に積み重なって、
“飲み物以上の価値”を生み出しています。
だから原価率が低くても、スタバの一杯が「安っぽく」感じない理由がここにあります。
“第三の場所”という文化が価格を支えている
そして、スタバの本当のすごさはここからです。
スターバックスの中心思想である「Third Place(第三の場所)」。
家でもなく、職場でもなく、もうひとつの居場所をつくる。
このシンプルなコンセプトが、空間設計・接客・商品設計のすべてに深く浸透しているんです。
要するに、スタバの価格はコーヒーの対価ではなく、
「第三の場所を維持するための投資」でもあるんです。
この視点を知ると、値段に対する感じ方がガラッと変わってきます。
スタバの価格は“体験を買うためのチケット”
僕が取材していて一番感動したのが、この“体験価値”の考え方。
スターバックスの価格って、実はラテの味ではなく、
“特定の心の状態にアクセスできるチケット”みたいなものなんです。
- 気持ちを整えたいとき
- 集中したいとき
- リセットしたいとき
- 自分を大切にしたいとき
この「状態」をつくる装置としてスタバが機能しているから、
僕らは値段以上の“納得”を自然に感じてしまうんです。
「ラテの温度は、あなたの一日の温度になる。」
そして最後に、この一杯が持つ“変化の力”。
スタバのラテはただ喉を潤すだけじゃないんですよね。
一日のテンション、選ぶ言葉、歩き出す速度さえ変えてくれる。
僕は何度もそれを実感してきました。
だからこそスタバの価格は、
“飲む前と飲んだ後の自分の違い”の価格なんです。
これが、原価では絶対に説明できない部分。
まとめ──原価が安くても“高い価値”を届けられる理由

スターバックスの記事を書くとき、僕はいつも最後の章でテンションが上がります。
ここまで見てきたすべての要素が、一杯のラテの中で“一本の線”につながるからです。
原価を調べて、価格の裏側を深掘りして、数字とブランドの構造を追いかけてきて……。
それでも結局、最後に残るのはひとつのシンプルな感覚。
「ああ、この一杯ってやっぱり満足するよね。」
スタバの価値は数字には宿らない。
でも、体験の中にはしっかり存在する。
ここが、何度調べても面白いところなんです。
原価は安い。それでも価格に“納得”できる理由
改めて、この記事で追いかけてきた“スタバが選ばれ続ける構造”を整理すると、こんなにあります。
- 一杯あたりの原価はたしかに安い(これは揺るがない)
- でも価格は“体験価値”によって丁寧に積み上げられている
- スタバは「プレミアム価格戦略」で価値ベースの価格設定をしている
- 空間・接客・香り・安心感といった無形の価値が強く作用している
- 日常を整える“儀式性”が価格をむしろ肯定させている
- どこへ行っても同じ安心が手に入る“ブランド体験の一貫性”がある
- 結果として、原価では到達できない満足感がちゃんと成立している
僕らはスタバのラテを手に取るたび、飲み物以上のものを受け取っています。
それは、「自分に戻るための時間」だったり、「気持ちを整えるスイッチ」だったり。
そして、そのための価格なら——高くても安くても、自然に腹落ちしてしまう。
記事を書きながら改めて思いました。
スターバックスって、本当に“体験を設計するブランド”なんだと。
最後に、この一文をそっと置いておきます。
「湯気の向こうに、昨日より少し優しい自分がいた。」
僕はこの瞬間こそが、スターバックスの価格に宿る“最大の価値”だと思っています。
よくある質問(FAQ)
Q:スターバックスの原価率は公開されていますか?
A:ここは多くの人が気になるところですよね。
結論から言うと、ラテやフラペチーノの商品別の原価率は非公開です。
公開されているのは、企業全体の売上原価(COGS)といった財務データのみ。
実際の商品原価率は“ブランドの核”に関わる部分でもあり、企業秘密として守られています。
Q:スタバのドリンクの原価は本当に安いのですか?
A:これは意外と知られていません。
コーヒー豆だけで見れば、確かに一杯数十円レベルという推定が多いです。
ただし、スタバの価格を決めているのはそこだけじゃありません。
賃料・教育・ブランド維持・品質管理など、多くの“見えない原価”が積み重なることで、あの価格が成立しています。
「原価が安い=儲けすぎ」ではなく、原価の考え方がそもそも違うと思っていただく方が近いです。
Q:ラテやフラペチーノの原価はどれくらいですか?
A:ここもよく聞かれます。
残念ながら、正確な数字は公開されていません。
ただ、有志による試算や専門家分析では、「原材料原価は販売価格の一部にすぎない」という点で一致しています。
スタバの場合は、空間・人・体験といった“無形の価値”に多くのコストが投じられているのが特徴ですね。
Q:価格が高いのに、なぜスタバは選ばれ続けるのでしょうか?
A:ここは僕自身、研究し続けていて飽きないテーマです。
スタバは「第三の場所」というコンセプトを軸に、
空間、接客、一貫した安心感という体験価値を提供しています。
人は“コーヒー”を買っているのではなく、「心が整う時間」を買っている。
この心理構造が、価格への納得感を強くしています。
Q:他のコーヒーチェーンと比べて、スタバの原価率は高いですか?
A:ここは比較が難しいポイントでもあります。
なぜなら、チェーンごとにビジネスモデルが根本的に違うから。
スタバは他社よりも空間デザイン・人材育成・ブランド投資に力を入れており、
それが価格にも体験にも反映されています。
つまり、単純な「原価率比較」では測れない領域で戦っているチェーンなんです。
参考情報・出典
本記事では、スターバックスの原価構造や価格設定を理解するために、複数の信頼性のある情報源を参照しています。まず、Starbucks Corporation の財務情報として Macrotrends が公開する売上原価(Cost of Goods Sold)データを利用し、同社の原材料コスト全体を把握しました。さらに、GuruFocus による売上原価の TTM(直近12か月)分析は、より最新のコスト動向を把握する参考として活用しています。
価格戦略の背景については、Emory Economics Review の「Starbucks Pricing Strategy」が、スターバックスがプレミアム価格戦略を取っていることを示しており、本記事の「原価ではなく価値で価格を決めている」という視点を補強しています。加えて、Medium の「How Starbucks convinced America that $7 coffee is normal」は、スタバがどのように体験価値を価格に転換し、“高いのに選ばれ続けるブランド”になったのかを、消費者心理の観点から解説しており、心理構造のパートに説得力を与える情報源となりました。
![]()


コメント